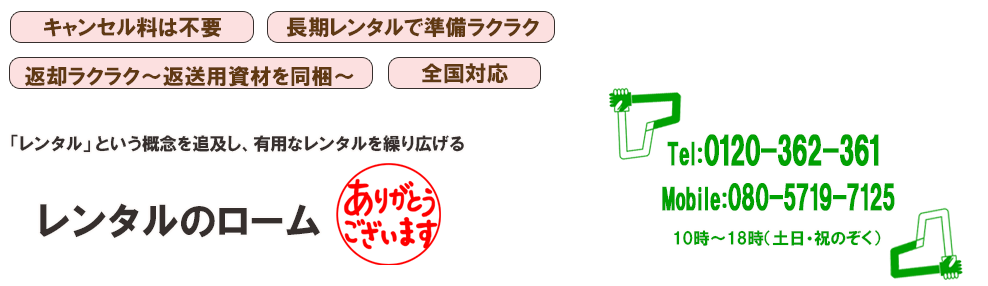福岡市の端っこ、筑紫野の家電量販店の棚の上に、「加湿器くん」は静かに並んでいた。
白くて丸っこいボディ、ミストの吹き出し口は少し曲がっている。展示機とはいえ、彼は心の中で誓っていた。
「オレは、福岡の空気を潤す男になる。」
その日、加湿器くんは若い女性に買われた。
彼女の名前はユウカ。博多駅近くで働くOLで、マンションの室内はエアコンでカラカラだった。
「乾燥しすぎて喉がイガイガするのよね。あなた、頼むわね。」
こうして、加湿器くんの活躍の日々が始まった。
ユウカは食べるのが大好きで、冬の夜にはよく友人を招いて「もつ鍋パーティー」を開いた。
部屋に人が集まり、湯気が立ちのぼり、加湿器くんはミストを休めた。
「今日はオレの出番はないな……もつ鍋、強い。」
だがある日、もつ鍋の湯気が上昇しすぎて、火災報知器が鳴ってしまう。
「これは危ない! 湿度調整はプロに任せなきゃ!」
その日から加湿器くんは、鍋パーティーの日でも微細なミストをコントロールし、湿度60%を死守する“霧の番人”となった。
ある春の日、ユウカは加湿器くんを連れて太宰府へ出かけた。桜が舞う参道、香ばしい匂いの中で梅ヶ枝餅をほおばりながら、ユウカが言った。
「来月、私は東京に転勤なの。でも、あなたは……どうしようかな。」
加湿器くんは静かにミストを吐いた。東京へ行けば、また知らない乾燥と戦わねばならない。でも彼の心には、福岡の湿った風、もつ鍋の蒸気、雨の匂いが根を張っていた。
その夜、ユウカは決めた。
「あなたは、福岡に残ったほうがいい気がする。きっと、まだ潤すべき人がいる。」
それから数日後、加湿器くんは福岡市内の小さなコワーキングスペースに譲られた。天神のオフィス街の一角にあるその場所では、多くの人がパソコンに向かい、日々忙しく働いていた。
「午後になると、エアコンの風で目がシパシパするのよね……」
「喉乾くよね……コーヒーばっかり飲んじゃうし。」
そこに現れた加湿器くんは、完璧な湿度管理でその空間を変えた。
心なしか、人々のタイピング音も軽やかに聞こえるようになった。
加湿器くんは今も、福岡の空の下でミストを吹き上げている。天神のカフェ、百道浜のブティック、そして大濠公園近くのスタジオへと、彼の活躍の場は少しずつ広がっていった。
「目に見えないけど、確かに届くものがある。」
それが加湿器くんの信条だ。
彼は今日も、福岡をしっとりと潤し続けている。